アトリエの近況などを紹介します^^
今日は、気になってた幼児教育についての本を読んでみたから、気になった内容と感想をざっくり紹介するよo(*’▽’*)/☆゚’
どんな人が書いたの?
著者の大久保博之さんは、元茨城県教育委員会院長でリリー文化学園の理事長さんなんだって。
お母さんは、リリー文化学園の創設者です。
仕事で忙しかったため、子育てや家庭のことは手が回っていなかったようです。
そのときに合った学習をさせよう
3歳までは、原始的な脳が発達する時期。
よく寝て、よく食べて、身体を動かすことが大切。
親と一緒に遊び、喜怒哀楽を思いっきり発散させよう。
3歳以降から「読み書き・そろばん」。
何歳になってからでも身につけられる。
9歳が脳の器の大きさの「臨界期」。
×プログラミング・トレード(お金)・特定のスポーツオンリー(色々やらせよう)
1〜3年生 タイピング
大きくしたい「6つの器」
- 言語的知能……国語
- 論理数学的知能……算数
- 音楽的知能……音楽
- 絵画的知能……図工
- 空間的知能……算数・体育
- 身体的知能……体育
器を大きくする「五感を使った体験」
上に挙げた6つの器を大きくするためのトレーニングが紹介されていました。
五感を使ってリンゴを描こう
- リンゴが出てくる絵本を読み聞かせる。
- 本物のリンゴを与えて、色・触覚・香りなど実物と接して感じたことを聞く。
- リンゴをコンコン叩いて「おしゃべりしてみよう」と声をかけ、子どもの耳へ持っていく。
- リンゴを切って食べる。香りや触覚を感じさせる。
- 以上のステップを踏んでからリンゴの絵を描かせる。
にゃあは絵画教室に通っていたし、大学院でも図画工作の授業を題材にしてたから、この五感を使うというのは面白いと率直に思った。
ただし、このステップが正しいかは別だけど。
ここは、各個人でアレンジしてもいいのかなぁと思った。
他にも、日常生活や体験を行うのに、この感覚とこの感覚を鍛えることができる!と、意識して体験することで、子どもの器の大きさの成長は格段に伸びるという。
確かに「この遊びにひと工夫加えたら、○○知能だけじゃなく××知能も伸ばせそうだな」と意識できるとやらせることも変わっていきそう。
たった一つの質問で、子どもの適性がわかる?
そのたった一つの質問とは…
「○○ちゃんは、海と聞いてまず何を思い出す?」
- 視覚……「青い海・白い波」など、ビジュアルイメージ
- 聴覚……「波の音・カモメの鳴き声」など、音のイメージ
- 嗅覚……「潮の香り」など、ニオイのイメージ
- 触覚……「冷たい水・砂浜のジャリジャリ」など、触感のイメージ
- 味覚……「海水の塩辛さ」など、味のイメージ
…これは、先生が思ってることなんだろうなぁ。楽しむ感覚でやるには良さそう。
感動を生み出す「4つの体験」
子どもは体験を通した感動によって経験が記憶に深く刻まれる。
これが6つの器を大きくすることにつながる。
- 文化体験……新しい知識や刺激、生活習慣に触れる体験。
- 運動体験……身体を動かす体験
- 自然体験……自然や世の中の現象に触れる体験
- 競争体験……目標を持って他者と競い合う体験
親が子どもに与えたいもの
- 24色以上の色鉛筆
- 図鑑
- カラフルな整理箱
- キャンプ体験
- 農村(高齢者との)生活体験(3日間お泊まり)
- 折り紙
- 偉人伝
- アナログ時計
- 家族写真を飾る
- ご褒美シール(ご褒美は最初に与えて、うまくいかなかった場合に没収するのが効果的)
- 子どもの睡眠時間
- ご飯の朝食
本を読んだ感想
これからちゃもを育てていくにあたって、実践したいと思える取り組みがあり、参考になった。
おじいちゃんおばあちゃんの家に何泊か預かってもらう体験もさせてあげたいと思った。



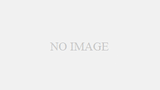

コメント